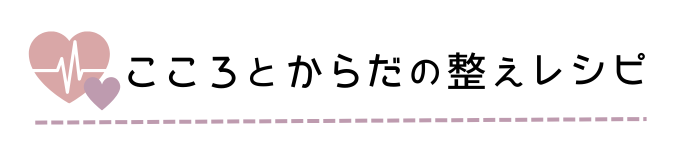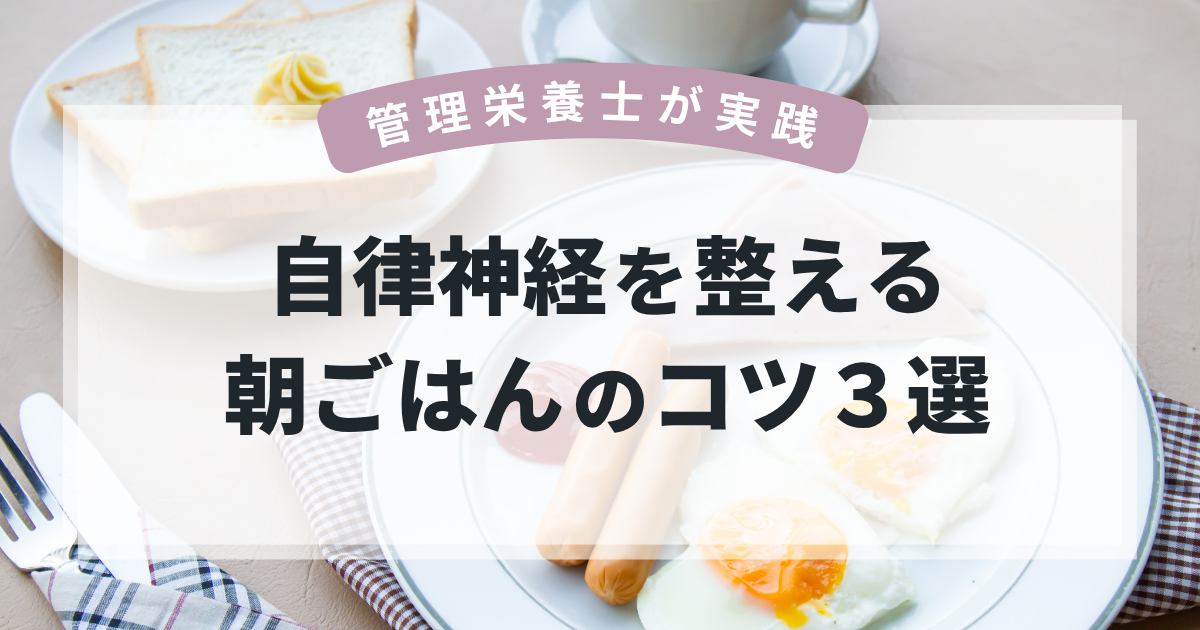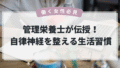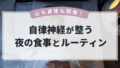「なんだか毎日疲れやすい…」それ、自律神経の乱れが原因かも?
朝スッキリ起きられない、気分が落ち込みやすい、やる気が出ない…。
それはもしかすると、自律神経のバランスが乱れているサインかもしれません。
自律神経は、生活習慣と密接な関係があります。特に影響を受けるのが「朝の過ごし方」
その中でも朝ごはんの内容はとても重要です。
今回は、管理栄養士が実践する、自律神経を整える朝ごはんのコツを3つご紹介します。
そもそも自律神経とは?
自律神経は、体の働きを自動でコントロールしてくれる神経のこと。
主に以下の2つの神経から構成されています。
交感神経:活動モード(朝~昼)
副交感神経:リラックスモード(夜~眠)
この2つのバランスが崩れると、不眠・イライラ・だるさ・胃腸の不調など、心身の不調を招きます。
特に現代人は、ストレスや不規則な生活習慣で交感神経が過剰に働きすぎてしまい、自律神経が乱れがち。だからこそ、毎朝の朝食でリズムを整えることがカギになります。
管理栄養士が実践!自律神経を整える朝ごはんのコツ3選
① 温かいもので「内臓」を起こす
朝は体温が下がっており、胃腸もまだ本格的に働いていません。そんなときに冷たいものを摂ると、交感神経が優位になり、自律神経の乱れに繋がります。
まずは起き抜けの白湯を1杯飲むこと。
味噌汁やスープももちろんオススメ!特に味噌は発酵食品で腸内環境を整える効果もあり、自律神経の安定にも◎。前日の残り物や即席の味噌汁、スープも上手く活用して実践してみてください。
② 良質なたんぱく質で「セロトニン」をつくる
朝にたんぱく質をしっかり摂ると、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンが作られます。セロトニンは、自律神経の調整・メンタルの安定・睡眠の質向上に深く関わっています。
おすすめ食材
- 卵(ゆで卵・スクランブルエッグ)
- 納豆・豆腐
- ヨーグルト・チーズ
- 鶏むね肉・鮭 など
ポイント
炭水化物とセットで摂ることで、たんぱく質の吸収がスムーズになります。
③ よく噛んでゆっくり、副交感神経を優位に
朝は忙しくて、つい「ながら食べ」「早食い」になっていませんか?でも実は、「よく噛む」「ゆっくり食べる」ことが、自律神経を整える近道なんです。
噛むことで副交感神経が優位になり、体がリラックスモードに切り替わります。
ベストは一口30回噛むこと
そんな時間がない!って方はまずは1口20回噛むことから意識してみましょう。
ポイント
スマホやテレビを見ながら食べない
“噛める食材”を意識する(例:野菜・雑穀・ナッツ)
自律神経を整える朝ごはんのモデルメニュー
\時間がなくてもOK!栄養バランスを意識した組み合わせ/
ごはん食の場合
ご飯+納豆 or 卵(+野菜たっぷり味噌汁)
パン食の場合
全粒パン+ゆで卵 or チーズ(+温かいスープ)
コンビニ食の場合
おにぎり+ゆで卵(+カップ味噌汁)
(おにぎりの具材は鮭・ツナマヨなど少しでもたんぱく質が摂れるものを!)
甘くない惣菜パン+サラダチキン(+カップスープ)
朝なかなか食べられない場合
ヨーグルト(無糖 or 甘さ控えめ)
フルーツ
自律神経を乱す朝食習慣に注意!
以下のような習慣は、自律神経のバランスを乱す原因に!
・冷たい飲み物
朝からアイスコーヒーは身体を冷やし、カフェインの作用で急に交感神経が優位になるため自律神経が乱れる原因になります。
・菓子パン・スイーツなど炭水化物のみの朝食
菓子パンやスイーツは糖質が多く、食物繊維やたんぱく質が少ないため、食後すぐに血糖値が急上昇します。血糖値の乱高下は自律神経が乱れる原因になります。
・朝食抜き
空腹状態で活動を始めると、身体は「ストレス」と感じて交感神経が過剰に働き、イライラや緊張、不安感を引き起こすことも。さらに、空腹時間が長くなると、次の食事で血糖値が急上昇しやすく、自律神経が乱れる原因になります。
まとめ|朝ごはんでこころとからだのリズムを整えよう
自律神経を整えるには、特別なことをする必要はありません。
「温かいものを食べる」「たんぱく質を摂る」「よく噛んでゆっくり」――
この3つのコツを意識した朝ごはんを、毎日の習慣にするだけで、心と体がぐんとラクになります。「なんとなく不調…」が続いている方こそ、どれか一つだけでも出来そうなものがあれば、今日から試してみてくださいね!
自分を整える第一歩は、朝食からはじまります。